インタビューvol. 36 神谷俊さん「見えない世界を観る 」
複雑なものごとを紐解いていくことは楽しいですし、紐解いた結果にまだ見たことがないような価値観やメカニズムが埋まっていたりするとワクワクします。好奇心があるから領域を規定しないし、膨大な文献を読むことも厭わないし、フィールドにも積極的に赴く。それが自分の「眼」を強くしているのだろうと思います。
 インタビュー
インタビュー
複雑なものごとを紐解いていくことは楽しいですし、紐解いた結果にまだ見たことがないような価値観やメカニズムが埋まっていたりするとワクワクします。好奇心があるから領域を規定しないし、膨大な文献を読むことも厭わないし、フィールドにも積極的に赴く。それが自分の「眼」を強くしているのだろうと思います。
 インタビュー
インタビュー
自分はダメと思っているとき、自分のいいところが見えなくなってるんですよね。そこをちゃんと思い出せば、本当はみんなもっとちからを発揮できるのに、ついつい人と比べてしまいがちです。
 インタビュー
インタビュー
一人ひとりが自分らしくハッピーに働くこと、生きることをテーマにさまざまな場で活躍している島田由香さん。ぐんぐん…
 インタビュー
インタビュー
僕はいろいろなジャンルのものを面白がって見ていると思います。あれに使えそう、これに使えそうと考えたりしています。
面白いヒトやモノやコトに出会ってしまうのが、人生の最大の喜びだと思うし、そこから広がっていきます。
 インタビュー
インタビュー
生態系は誰かがコントロールして、「こっちに行くぞ!」とか、「こういう植物のばすぞ!」としているわけではないんです。環境に合わせてそのときに最適なものが繁殖するのと全く一緒で、構成する一人ひとりが、一番よかれと思ったことをやった結果、生態系は一番よい方に進化することで組織が動くと思っています。
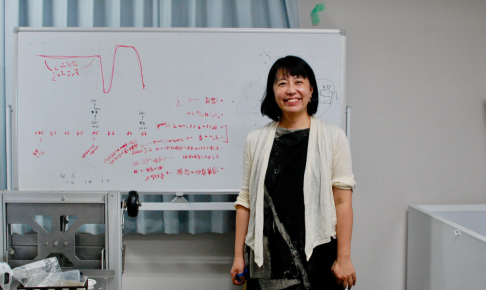 インタビュー
インタビュー
最終成果みたいなものは、500年後か1000年後かもしれませんが、何かひとつでも、自分だけが初めに知る発見というのは、常に目の前に小さな人参がぶら下がっているような状態なんです。
 インタビュー
インタビュー
違いを知ったうえで、これが自分には合うだろうということを、それぞれの人が見つけないといけません。あとは何のために学んでいるのかという目的ですね。時代が変われば子どもも変わります。いろいろな選択肢・可能性を示すことができても、その中で自分が何を選ぶかはその人が考えなくてはいけないことです。
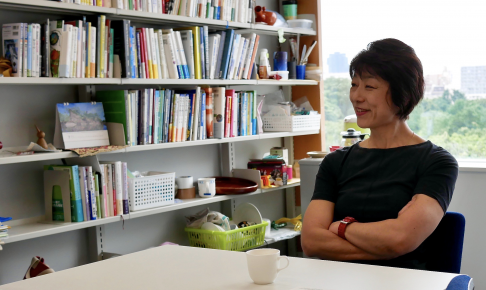 インタビュー
インタビュー
「サステナビリティ」というのは、自然環境のことだけではありません。人や動物、植物などとも関係し合っています。だから「おかげさまを忘れないでね」と学生たちに伝えています。
 インタビュー
インタビュー
人に対する誠実さがお米に出るような気がします。お米は生産者を映し出すので本当に面白いんです。
 インタビュー
インタビュー
いつでもお互いに心を素っ裸にできることです。子どもたちのことは、同時代を生きている仲間だと言っています。「俺は昭和生まれで、お前たちは平成生まれだけど、時代云々じゃなくて、いま、この時代を共有してい生きている仲間なんだ」と言っています。