編集者の川村庸子さんは、アートプロジェクトや組織、コミュニティに伴走しながら、本などのメディアをつくっています。西村佳哲さんの「インタビューのワークショップ」で出会いました。ワークショップはひたすらに「話す・きく」の濃密な時間でした。そんな時間を一緒に過ごした川村さんが何を大切にしているのか、なぜ編集なのか、いつかきいてみたくて、インタビューをお願いしました。
「編集者」というあり方
ーー川村さんの編集した本などを見て、まだ世界に生まれていないものをつくっているんだなと思いました。最初からかたちがあったのではなくて、見えない何かを誰かと掘り起こしながらつくっているんだろうなと思ったんです。
そうですね。あるものをどうかたちにするかという意識はあります。私が扱っているのは人の営みや記憶、出来事など動き続けているもので、そこに編集という技術を用いて、本やWEB、イベントというかたちを与えているから、そういう印象を持ってくれたのかもしれません。
私自身はもともと小さいときから本ばっかり読んで生きてきたので、自分の中でほかのことよりもそこに対する感受性が高いんですよね。一番見えるっていう感じ。ことば、特に本のかたちをしたものに対しては、「ここのスピードをもうちょっとゆっくりさせたい」「ここは抜け感がほしい」というように、その内容だけでなく、リズムや速度、重さなどのテクスチャーなどについても事細かにイメージが湧いてくるんですよ。とは言え、実際はクリエイションに入るまでには道のりがあって、対話の時間を持つ習慣をつくったり、資料を集めて読み込んだり、情報共有や予算分配を見直したり…まずは活動に参加しながら、そのチームの端っこにいるひとりとして「つくる」環境を整える時間があります。
いくらやりたいと思っていても、余白がないと記録やコミュニケーションに関する活動って後回しになっちゃいますから。そうしたプロセスを通して、その人たちや活動を身体に入れたり、課題やアイデアの種を掴んでいく。小さな組織体だとものごとの動きが早いので、それを経てやっとつくるための議論や作業に入れるようになることがほとんどです。
なので、一般的に言われている編集の枠外のことも多いのですが、最終的に自分が責任を持てるというか、自分が持っているものを一番使えるのはことばや本などのメディアだなと思っているので、いまのところ「編集者」と名乗ることにしています。
ーー出来上がるもののよい、悪いはどうやってわかるのですか? それはどんな感覚ですか?
このプロジェクトや組織の人格や状態がどういうもので、それに一番フィットするかたちは何か、ということだけを考えているような気がします。たとえば、植物には上に伸びるものと横に広がるものがありますよね。それと一緒で、そのプロジェクトがどのような生命力を持っているかということがまずある。そこから今いる現在地を把握して、「もうちょっとこっちの方に伸びていくといいんだろうなあ」という方向を一緒に見つけていきます。
何かをつくるということは親密な関係にならざるを得ないから、ちゃんと関係が育まれていればやるべきことは自然と見えてくる。これは誰にでもある力だと思いますが、それを私は編集者として意識的にやっているんだと思います。
そこにあるけれど、まだ見えていないもの
ーー「意識的に」とはどんな感じですか?
一応これでごはんを食べているので、いつか何かわかる、じゃなくて、いつまでにこういう状態になるという時間のコントロールをしたり、一つひとつのやりとりの精度を高めるという感じですかね。
これまでどのような経験をしてきたのかというような個人的な会話をメンバーと交わしたり、その土地や業界のことを知識的に調べたりもしますが、一番は声をかけてくれた人たちの活動に参加して、その土地のことばをきいたり、一緒にご飯を食べたり、彼らの周りにいる人たちと出会ったりしながら身体化していくというか、自分の中に何かを溜めていきます。
そうすると「このプロジェクトはこういう奴なんだな」というのが見えてきて、そこに対して何を担えるかがわかる。「じゃあ、こういう機能のあるものが必要だ」「それはこういう構造で…」と、だんだん誰と何をつくるべきかのイメージが立ち上がってくるんです。
ーー見える感じですか?
うーん、見えないけれど、手ごたえはあるかな。これまでに読んだいくつかの本や映画のことを思い出したりします。
ーー何も見えてこないときはないですか?
ないですね。そもそも、そういったつくる以前の時間を持てているだけで、ある種、もう半分以上は成功していると思うんです。第三者と対話をするプロセスに価値を感じていて、そこに時間とお金をかけている。そこに立ってくれた時点で大事なことは共有できているので、そういう相手とはやるだけです。もちろん歩みが停滞することはありますが、抜ける感じは常にありますね。あと何回かこの状態を繰り返したら絶対次の段階に進むなと。
対話がちゃんとできているときって、ほんとうにいろんなことが起きますが、おもしろいのは自分と相手の意見があってどちらが答えかということではなくて、そのあいだにあるものが徐々に浮かび上がってくるんですよね。
異なる複数の人が真剣にことばにしようとすることを通して、意見を統合するのではなくて、それぞれが照らしているものはこの辺だなという部分が見えてくる。そこにはプロジェクトや組織の生命力のようなものがあって、それには不完全だけれどかたちを与えていけるんじゃないかと思っています。
たぶん私が第三者として外から入ることで光源が増えるので、普段よりも見えやすくなるんだと思うんですよ。つまり、既にそこにあったけれど見えにくかっただけ。だから、いつも「なーんだ、やっぱりこれだったね!」とどこかで知っていたことを一緒に発見する感じがあります。
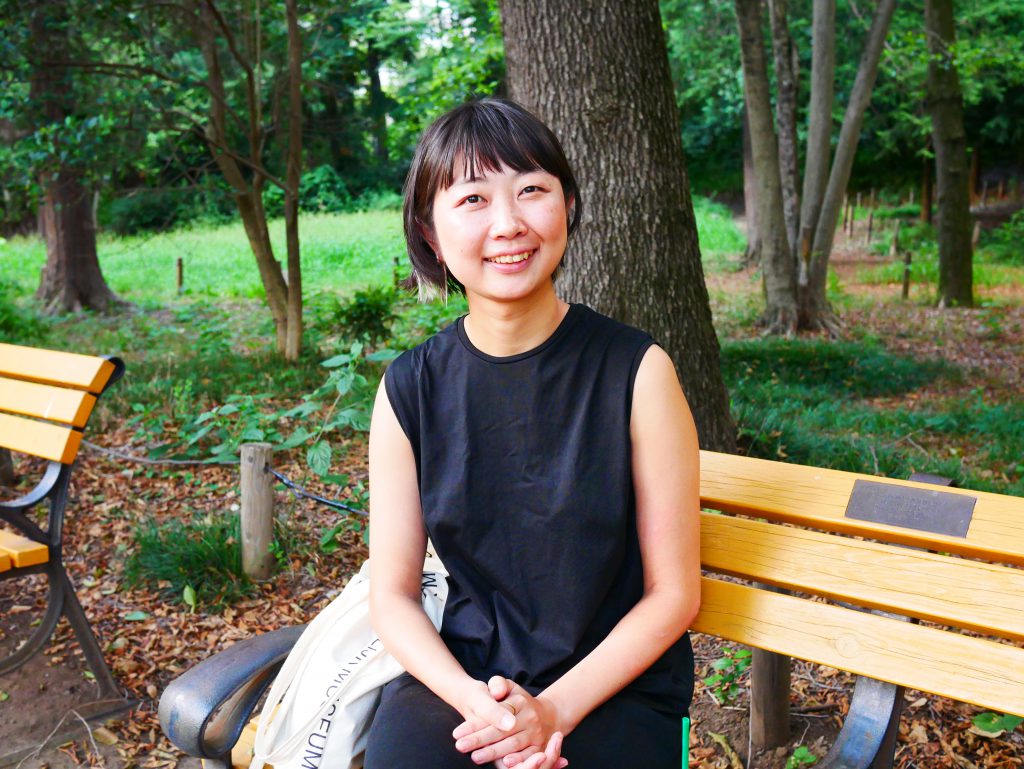
「生きる」を見る
ーーいつも「編集者」だ、という軸が生活の中にあるのですか?
特に意識はしていませんが、もうそうなっちゃっています。日常的に自分は右利きだと意識していなくても右利きなんですよ、圧倒的に。それと同じような感覚です。
私は私としての「編集」のやり方や、それを通じて見たいものに触れる技術をもうちょっと高めたいなあと思っています。いったい何をやっているんだろうと途方に暮れることもありますが、でも確かにずっとやっていることがあるんですよね。それは何年かかるかわからないけれど、自分の中でよりはっきりさせてきたいです。
ーー川村さんが見たいもの、触りたいものはどんなものですか?
何ですかね、自分でもよくわかんないんですよね。プロジェクトの立ち上げや記録、組織の棚卸に伴走することが多いのですが、そこで起きていることは、本当に名づけようがないんです。それこそ敢えてことばにすると「誰かとともに生きていくこと」や「人生」みたいなことで…。とにかく目の前で起きている素晴らしいことを、どうにかかたちにしたいと思いながらやっていますね。
出来事や関係性をことばにしたり、かたちを与えるということは暴力的なことです。どんなに力を尽くしても、やっぱりそれそのものにはなれない。ただ限りなく近づく方法があるのではないか、あるいは大事なものだけは掬うことができないかといつも試行錯誤しています。
一緒に居続ける
ーー最近、考え抜くというのはすごく難しいことだなと思っています。川村さんは『言葉の宇宙船 わたしたちの本のつくり方』で、編集について「一冊の本をつくる全プロセスにおいて、一番迷い、動き、考えること」と書いていましたが、どこまでいったら考え抜くことになるのでしょう?
私はあまり考え抜くという感覚はなくて、考え続けるという感じです。そのことと「ずっと一緒に居続ける」という感じでしょうか。常にそのことが身体の中にある感じ。
参考になりそうな本を読んでいても、まったく関係のない話をしていても、いつもそのときやっているプロジェクトのことが身体の片隅にあって、そのことを思い出したり、考えたりしながら暮らしています。だから、同時にあまりたくさんはできないんですよね。
ーー原稿でいうと、ここで終わりだと決める瞬間はどんなときですか?
原稿で言えば、一週間ほど一緒に過ごします。手を動かしていると、もうこれ以上ないなというときがやってくるんですよ。一度集中してかたちにしたあとは、毎朝、一回読んで気になるところに手を入れて、それを一週間くらい繰り返すと、ああ、もういまの自分だとここまでだなという感じになるんです。
毎日その日の気持ちや体調があって、次の日はまた違う自分が読むわけですよね。それをやっていくと、心身がもたらす小さなブレのようなものや日々の経験が統合されていって、収まるところがある。一週間あれば、毎日違う7人の私が原稿をチェックするようなイメージです。そうやって自分ひとりでできるところまでやったら、プロジェクトメンバーにパスをして別の視点をもらいます。
ふたつの手触り
ーー川村さんが編集について語るときによく使う「手触り」ということばが印象的です。
それはたぶんふたつの意味で使っていて、ひとつは「実感」ということかなと思います。
最近体力が落ちすぎてジムに通っているのですが、トレーナーに胸を開くように言われたんですね。でもそもそも胸が開けていないわけで、よくわかんないなと思っていたんです。
でも、次に「鳩尾(みぞおち)を突き出すように」と言われたら、その瞬間にぐわっとイメージが湧いて急に身体の使い方がわかったんです。同時に腹筋や下半身の使い方もわかった。そういうちょっとした一言が針穴に糸を通すように感じられたり、たった一枚の写真がイメージを運んできて、全身で理解する瞬間がある。
それは大事な記憶が急に蘇ってきて、なんで私はこのことを忘れていたんだろうなと思う感覚に近い。そういうことを私は「手触り」と言っていて、身体知のようなものを呼び起こすものなんじゃないかなと思っています。
ーーことばを見ていて、ぐわっとイメージが湧いてきたりするんですか?
ぐわっとだったり、じわじわ沁み渡るような感じだったり、身体中を駆け巡る感じだったり、いろいろです。考えるというのは脳で行っているように思われがちですが、実際は内臓や皮膚など全身を使っているわけですよね。だから「腑に落ちる」とか「腹わたが煮えくりかえる」なんてすごくいい表現だなと思う。肉体を使えるというのは、生きている者の特権ですから。
もうひとつは、ことばや物質の「質感」としての手触りです。風が一瞬吹いただけで、朝起きて窓から光が差し込んだだけで、人の気持ちや考えがぱっと変わるときがありますよね。そういうとき、いかにわたしたちが抽象的で些細な事柄に支えられて生きているかということを思い出します。そういうことを感じながら生きていきたいし、自分がつくるものはテクスチャーを大事にしたいなと思っています。

(インタビュー:寺中有希 2018.7.26)
プロフィール
1985年埼玉県生まれ。学習院女子大学国際文化交流学部日本文化学科卒。
在学中からasobot inc.に参加し、ディレクターとして、企画・編集・地域のリサーチを行う(~2014年)。編集した主な媒体は、『GENERATION TIMES』(ラフォーレ原宿、2004年~2010年)、『earth code』『survival ism』(ダイヤモンド社、2010年、2011年)、WEB『復興の教科書』(文部科学省、2014年)。NPO法人シブヤ大学の企画・運営・姉妹校立ち上げの中間支援(2006年~2010年)。オルタナティブスペース「undō」代表(2014年5月~2015年12月)。
近年は、ABI+P3共同出版プロジェクト『言葉の宇宙船 わたしたちの本のつくり方』、Art Support Tohoku-Tokyoジャーナル『東北の風景をきく FIELD RECORDING』、復興公営住宅での音楽と記憶のプロジェクト『ラジオ下神白–あのときあのまちの音楽からいまここへ–』、学生とつくる武蔵野美術大学広報誌『mauleaf』など、さまざまなプロジェクトに伴走しながら編集を行っている。












PAlogo-300x116.png)